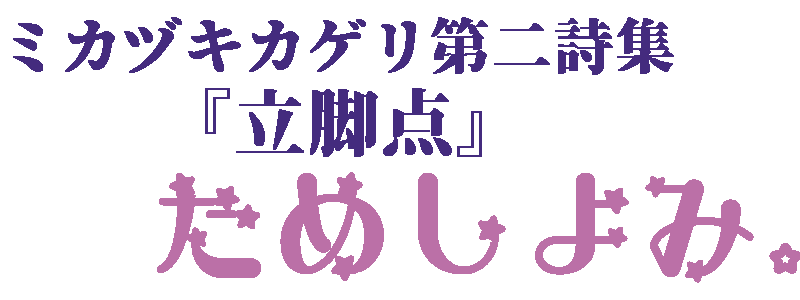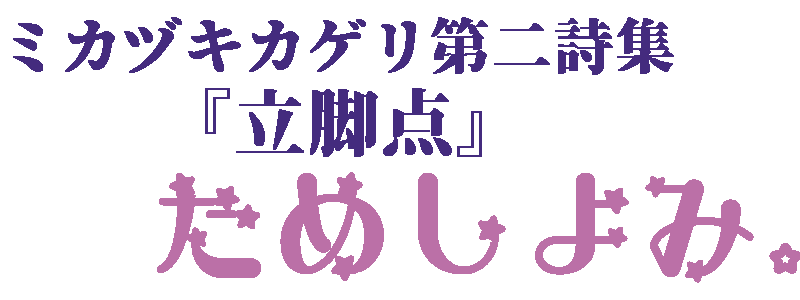
まず、全体的な感触として、「痛み」がやわらいでいる感じがします。もちろんいい意味でです。
痛切な体験、痛烈な感情は出ているのだけれど、どこかに「救われている」という安らぎが流れているように思います。
読んでいて、引き込まれたあとに、充実した爽快感が残るというか。(うまく伝えられなくてごめんなさい)
もしかしたら、カゲリさんの自分を見る視点が、第三者、というものを、読者に意識させるからかもしれませんね。
まず、[火星を想う]。
だからわたしは思うのだ。
『介助者と暮らすことは、
隔たった火星を想うこと』
であると。
繰り返し繰り返し、自分に云い聞かせるみたいにして。
なぜ火星なのか?
引用させてもらいましたが、「だからわたしは思うのだ。」という冒頭で、様々なことを考えさせられます。
「だから」の手前にあるものは何か。どのくらいの蓄積があって、「だから」に至ったのか。そこで喜びや苦しみ、嬉しさや哀しみを読者は想像しますが、そこでいわゆる「暗い重さ」のようなものは感じません。「だからわたしは思うのだ。」という断言が、その独特のあかるさにつながっているような気がします。
「だからわたしは思うのだ。」とは、本当に良く錬られた言葉だと思います。
その直後に「火星を想うこと」というフレーズが出て来ますが、ここでの「想う」と「思う」の差異によって、作品にエンジンがかかっている気がします。
「思う」と「想う」が、互いに引き立て合って、この詩集全体を起動させる力になっている、と言うか。
たぶんなんですが、「思う」から「想う」に至る飛躍が、この詩集のテーマなのだと感じました。海のような「思う」からせり上がる「想う」。この「想う」の尖端が、ときに痛切な響きとなって、詩集を牽引している。([むらさきいろ]の「思い出」と「想い方」、「想う」という言葉は使っていないけれど[まだわたしにも]の「キモチ」、[旅立つきみへ]の感情の露出、などに見られます)。
そして、それが作者から読者へ、直にぶつけるのではなく、何かを経由して伝わってくるところに安堵感と、「詩」たる所以があるような気がするのですね。
([動物園]の「すてきな動物園をくれました。」に最も顕著なあらわれをしているかもしれません)
[火星を想う]に戻ります。
「なぜ火星なのか?」と作者は自問していますが、この詩のなかに、すでに答えは出ているように思います。月でもない、太陽でもない、他者としての「火星」。その他者が作者と世界を媒介する=介助するものであるから、「火星」であることは言うまでもないことでしょう。その火星が遠く隔たっている、だからこそ「想う」。その「想う」という切実さが、そしてその切実が火星への〈信じたい〉という願いに支えられていることが、たとえば[山芋鉄板]の介助者との認識のズレとそれを受け止める充足感にもあらわれている印象を持ちました。
そして、その〈媒介するもの〉の究極と言えるものが、〈言葉〉であることは疑いもないでしょう。
作者と、世界を媒介するものとしての〈言葉〉。
その媒介が強く意識された詩集だからこそ、読者のなかには「自分も世界と接続できている」という安堵を与えるものになっているし(少なくとも私はそうでした)、〈言葉〉の研ぎ澄まされ方がいっそう「詩」として屹立していると言えます。([夜の点滅信号]、[憧憬]の言葉の切り取り方のうつくしさ!)
その集大成が[ひとりきり]のひらがな文と漢字の交差、そして「だからこわいけれど、/勇気を出してわたしは言葉を綴る。/これは手紙」なのだと思います。
その手紙がきちんと読めたかどうか、私にはわかりませんが、少なくとも私には、「ミカヅキカゲリ」という詩人からの手紙が届いたと、それがいちばんの感想です。